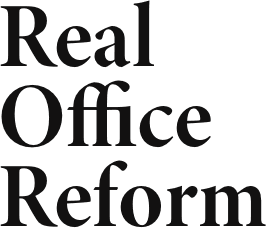オフィス移転のスケジュールや移転成功の秘訣
オフィス移転を成功させるのに大切なのは「目的」
オフィスの移転成功のポイントは、「移転の目的を明確にすること」です。オフィスの移転を考えはじめると、すぐにオフィスビル探しやレイアウトの検討に着手したくなりますが、移転先やレイアウトを考える前に、目的を明確にしましょう。
この際に注意したいのは、オフィスのイメージまで明確化することです。たとえば、「コスト削減」を目的に掲げた場合、賃料の安いオフィスが移転先の候補になるでしょう。しかしコストを削減だけに集中してしまうと、オフィスの快適性が担保できなくなるかもしれません。生産性や社員の満足度に影響します。企業の目的は、コストは削減しつつ、収益をアップさせることではないでしょうか。その場合、単純に家賃を下げるだけではなく、生産性が向上するオフィス環境、社員のやる気が向上するオフィス環境、優秀な人材を確保しやすいオフィス環境などが、賃料と同様に重要な移転の目的になるはずです。
移転を成功させるためには、オフィスでの働き方を具体的にイメージした上で、移転目的を明確化することがポイントとなります。移転先のオフィスでどのような働き方をしたいかというビジョンを考え、条件を決め、その条件に合うオフィスを探すことが大切です。
オフィス移転の目的を明確化するときの手順には、次の3つの手法があります。社風や企業理念などに合う方法で目的を明確にして、そのビジョンを社員と共有してください。新しいオフィスでの働き方のイメージが社員に伝わることで、前向きな移転につながります。
トップダウン型でのビジョン策定
トップダウン型では、経営陣が会社の方向性に合わせて目指すべき働き方の理想像を策定します。経営陣が策定したビジョンをプロジェクトメンバーや社員に共有し、各人がイメージするビジョンを取りまとめ、経営陣に意見を上申。この手順で、会社の方針に沿いながら現場の意見も取り入れたビジョンが策定できます。
プロジェクト主導型でのビジョン策定
プロジェクトメンバーが主導となり、理想の働き方のビジョンを策定してから経営陣に上申する方法。プロジェクト単位での上申なので、比較的取りまとめやすい方法です。現場からの積極的な意見が反映され、働きやすいオフィスが作れます。
ボトムアップ型でのビジョン策定
社員一人ひとりの意見を集約するのがボトムアップ型のビジョン策定です。アンケートシステムを活用して社員の意見を集めるのもいいでしょう。社員の意見を反映したオフィスを作ることができ、働き方の満足度が向上します。人材確保や離職率低下、ひいては生産性・売上向上が期待できます。ただし、ボトムアップ型でのビジョン策定を成功させるには、社員に企業の在り方や目標が共有されていることが条件です。それぞれが別の方向を見て意見を出し合うのではなく、同じ方向を見て意見を出し合ってもらう必要があります。
オフィス移転業者を選ぶポイントは?
サポート範囲を決める
「オフィスの荷物の移動だけを行う」「物件探しやレイアウト設計など総合的なサポートがある」「内装工事を担当する」「オフィス家具をコーディネートしてくれる」など、サポート範囲は業者によって異なります。どの範囲をサポートしてほしいか明確にして、そのサポートを受けられる業者を選びましょう。
独自サービスやアフターフォローの充実度
サポート範囲の次にチェックしたいのは、アフターフォローです。オフィス移転を進める中でトラブルが発生した際にどこまで対応してくれるのかをチェックしてください。中には書類申請代行までしてくれる業者もあるので、どんなアフターフォローがあると安心できるかを検討しておきましょう。
オフィス移転実績
外せないポイントは、実績です。オフィス移転は、移転先でスムーズに業務を開始できることが重要。家具や荷物をただ運搬するだけではなく、パソコンやプリンタを接続しなければいけません。オフィス移転の実績をチェックして、安心して任せられる業者を選びましょう。
オフィス移転にかかる費用
複数の業者に相見積もりを取ることで、適正な価格かどうかをチェックできます。相見積もりを取る際は、見積もりの有効期限に注意してください。移転費用は時期によって変動するため、期限を過ぎた場合は再度見積もりが必要です。
オフィス移転業者の評判
業者を選ぶ際は、評判を確認することをおすすめします。業者の公式サイト以外にも、利用者の口コミ情報を確認できると安心です。リアルな口コミを探し、信頼できる業者か判断する際の参考にするといいでしょう。
オフィス移転業者を選ぶ際の注意点は?
スケジュールや費用が見積と異なるときがある
オフィス移転は時期が重なりやすいです。業者にとっては繁忙期。見積もりを出してもらっても、見積もり通りにならない可能性があります。見積もりはあくまで提出してもらった時点での予定であることを理解しておきましょう。
一般的にオフィス移転の繁忙期は、1月から3月、そして9月から12月と言われています。可能であればこれらの時期を避けることでスムーズに移転しやすいです。
ネットワークトラブルが発生する可能性がある
移転先でスムーズにネットワークが使えることは、事業の継続性から重要なポイントです。ネットワークトラブルが発生すると、社内業務が滞ることはもちろん、取引先にも迷惑をかけてしまいかねません。しかし、配線や接続にミスがあれば、ネットワークトラブルが発生してしまいます。
ネットワークトラブルを起こさずスムーズに業務を行えるようにするには、移転先オフィスのネットワーク構築を専門家にサポートしてもらうのがおすすめ。接続機器が多いほど、配線や接続の設計は複雑になるため、自分たちで設計するのはトラブルの元です。
原状回復に伴う金銭トラブルが発生する可能性がある
移転先ばかりに気が取られてしまいますが、今まで利用してきたオフィスのトラブルも考慮しておく必要があります。重要なのは、原状回復です。基本的に原状回復してから退去することになるため、物件オーナーへ原状回復費用を支払うことはありません。しかし、場合によっては別途原状回復が必要だとして追加費用を請求されることがあります。その際は、内容の妥当性を確認しましょう。
また、敷金や保証金が返却されないといった金銭トラブルが起こることもあります。自力で解決が難しい場合は、弁護士など専門家への相談を検討してください。
オフィス移転のスケジュール(流れ)は?
オフィス移転は、約6ヶ月~1年間のプロジェクトです。スケジュールを管理して、スムーズな移転を心掛けましょう。大まかなスケジュールは以下のようになります。
- 移転計画立案
- 移転先選定と旧オフィスの解約
- レイアウトの決定
- 各種業者手配・備品関係の発注
- 引越し及び原状回復工事
- 各種申請書類の提出・取引先への連絡
- 移転完了
特に注意したいのは、解約とレイアウト、原状回復、関係各所への連絡です。各工程のポイントを解説します。
解約がいつまでに必要なのか要確認
移転の際は、現在のオフィスを解約することになります。解約通知の申告時期が決まっているので、いつまでに連絡が必要か確認してください。オフィスの契約では、一般的には退去日の3~6ヶ月前までの申し出に設定されています。いつまでに移転するのかというゴールから逆算して解約通知をするといいでしょう。
レイアウトは「ゾーニング」が重要
移転先オフィスのレイアウトを検討する際は、「ゾーニング」をしっかり考えてください。機能や用途ごとにスペースを区分けして、必要なものを必要な場所に配置するという考え方です。ゾーニングが明確になっていないと、社員の動線が混乱し、快適に働くことができません。来客者にも落ち着かない印象を与えてしまうでしょう。応接室は出入口近く、リフレッシュルームはオフィス中央など、理想の働き方に沿ったゾーニングを設計してください。
原状回復の工事内容は?
旧オフィスの原状回復工事は、解約日までに行う必要があります。原状回復工事の内容は、「家具・備品・パーテーションの撤去」「床や壁の加工を戻す」「床や壁の汚れのクリーニング」などです。入居の際にカーペットを敷いた場合は、撤去する必要があります。
原状回復工事に必要な期間は、元の状態と現状がどのくらい違うかによりますが、1ヶ月以上かかる可能性もあるため、解約日の2ヶ月前にはスケジュールが確定している状態にしておきたいです。
取引先への移転連絡の注意事項
オフィス移転の際は、取引先や金融機関など、関係各所へ連絡する必要があります。移転連絡のタイミングは、引っ越しの1ヶ月ほど前がいいでしょう。
移転連絡は、メールやFAXで問題ありません。ただし、重要な取引先の場合は、はがきでの通知も行います。はがきが担当者まで行き届かない可能性を考慮して、担当者には直接メール連絡も行うと安心です。
各種申請書類の提出期限は?
取引先だけではなく、公的機関へも各種書類の提出が必要です。主な必要書類と期限は以下の通りです。
- 年金事務所/適用事業所所在地・名称変更(訂正)届:移転後5日以内
- 労働基準監督署/労働保険名称・所在地等変更届:移転後10日以内
- 法務局/本社(または支店)登記申請書:本店の場合は移転後2週間以内/支店の場合は移転後3週間以内
- 税務署/異動届出書、給与支払事務所等の届出:移転後1カ月以内
- 都道府県税事務所/事業開始等申告書:移転後速やかに
- 公共職業安定所(ハローワーク)/雇用保険事業主事業所各種変更届:移転後10日以内
- 消防署/防火対象物使用開始届出書:移転日の7日前まで
- 消防署/防火対象物工事等計画届出書:移転日の7日前まで
また、必要に応じて、郵便局へ郵便物届出変更届を提出しましょう。