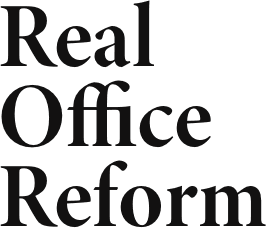コミュニケーションを
活性化させるための
オフィス創り
コミュニケーションを活性化させるにはどのようなオフィス創りが必要なのか、 オフィス移転・改修のコンサルティング会社である、ティーズブレイン代表の竹下氏に、導入する際の注意点や考えるべきことについて聞きました。
コミュニケーションが活性化する
オフィスを実現させるには
活性させたいのかを明確に

コミュニケーション活性といっても一概には言えません。普段あまりしゃべらない部署の人たちと偶発的なコミュニケーションをとってもらいたいのか、それとも近しい人たちとのコミュニケーションを活性化させたいのか、どのようなポイントでコミュニケーションを活性化させたいのかが重要です。
それにより、フリーアドレスやABWなのか、バーカウンター・カフェスペースなのか、MTGスペースなのか、検討材料が変わってくるのです。場合によってはオフィス環境を変えるよりも、アプリを使ってコミュニケーションを活性化させる方法もあります。
株式会社ティーズブレイン代表:竹下仁
コミュニケーションが活性化したオフィス改革事例
【事例①】株式会社イーウェルへの
オフィス改革事例

福利厚生サービスを生業としている会社としてオフィス移転前から健康経営を実践されていました。その最後の総仕上げとして、オフィスの契約更新と今後の増員対応の必要性に迫られたことを機に、オフィスを移転して「従業員が生き生きと働きやすい職場環境の具現化」を目指しました。

単なる設計プロジェクトマネジメント業務だけでなく、オフィス創りのプロセスに、事務局のほか若手従業員にも参画してもらいながら、オフィスのコンセプト創りから運用ルールの策定までかかわってもらうことを提案させていただきました。完成したオフィスは、従業員参画型でのオフィス創りが評価され、第1回ホワイト企業大賞を受賞(※2016年4月)し、従業員モチベーションとエンゲージメント向上につながりました。
その他、株式会社イーウェルへの
オフィス改革事例


【事例②】深田サルベージ建設株式会社の
オフィス改革事例

固定席での運用が原則ではあるが、コミュニケーションが図れるコラボエリアの新設や、集中して業務に取り組める集中ブースを設置する事で、連携を高めながらもメリハリをつけて業務に取り組める環境を構築させていただきました。

エントランスについては深田サルベージ建設様の海への思い(海と人の未来のために)を踏まえ、白を基調としたシンプルでクリーンな空間に、海と波をイメージとして青のポイントと曲線を用いる事によって印象に残る空間デザインをご提案させていただきました。
その他、深田サルベージ建設株式会社への
オフィス改革事例


【事例③】株式会社マーキュリア インベストメントの
オフィス改革事例

本工事により1フロアへのオフィス集約が完成、また運用ルール策定のサポートを行うことによりフリーアドレス導入以前の働き方から大きく変革が行われたプロジェクトとなりました。

テレワークの浸透(出社率5割)により、フリーアドレスを採用。ハイデスクやソファ席、コミュニケーション活性を目的としたビッグテーブルなどをオープンスペースに設けコミュニケーション活性化をご提案致しました。

既存区画の一角にフリーアドレススペースと開放感のある社長室を新設し、社員との距離感を縮め上下の役職を飛び越えたコミュニケーションが出来る空間を演出しました。

コミュニケーション活性化と同時に、集中エリアとして異なるタイプの個別ブースを複数設置し、自由度の高い執務エリアを構築しました。
その他、株式会社マーキュリア インベストメントへの
オフィス改革事例


【事例④】株式会社アトラスの
オフィス改革事例

今後もテレワークを進めていくという方向性を踏まえ、出社した際のコミュニケーションスペースを多く盛り込むことでコロナ禍でも「会社に来たくなる」オフィスづくりに取り組めたと思います。
その他、株式会社アトラスへの
オフィス改革事例


【事例⑤】株式会社レガートシップの
オフィス改革事例

社員が集まれるスペースとして、社長の強い希望でバーカウンターを設置しコミュニケーションを誘発する手助けとしています。
プロジェクトのスタート時には、予算の関係でバーカウンター設置は、あきらめていらっしゃいましたが、早い段階からコストコントロールをティーズブレインが行う事で、こだわりのバーカウンター設置を実現致しました。
その他、株式会社レガートシップへの
オフィス改革事例


【事例⑥】プレミアグループ株式会社様(大阪支社)の
オフィス改革事例

社員の「働きやすさ」を第一に考えるオフィスを創出するための拡張・改装プロジェクト。 コミュニケーション活性化や採用効果向上など、社員のモチベーションUPが期待できるレイアウトづくりに注力しました。

現オフィスで使用している家具や什器は最大限に活かしてコストを抑えながら、デザインは一変させ、 今までのオフィスから大きく進化した雰囲気を出すレイアウトになっています。
その他、プレミアグループ株式会社様(大阪支社への
オフィス改革事例



本物のオフィス改革をしませんか?もしオフィス移転、改修を考えているなら、ぜひこのメディアを読んでください。
本物のオフィス改革は従業員のエンゲージメントの向上だけでなく、業務効率化、生産性、売上向上に寄与します。
当サイトではオフィス改革の実際の成功事例をたくさん紹介していますので、事例を見ながら成功ポイントを見つけてみてください。
またオフィス設計や移転を機に改革を行うプロである株式会社ティーズブレイン監修のもと設計や移転時に抑えておくべきポイントもまとめています。
このような課題をかかえる
企業は
ご検討ください
- 従業員同士のコミュニケーションが希薄
- 業務の進捗やタスクなどがうまく共有されない
- オフィスの雰囲気が何となく悪い
- 従業員がなかなか定着しない

代表取締役社長 竹下 仁氏
“本当の意味でのオフィス改革を推進”
株式会社ティーズブレインは、オフィス改革を通して従業員へ企業理念の浸透やエンゲージメント向上などをコンサルする企業。経営層の「こうしたい」を汲み取り、単なる形だけの変革ではなく、従業員の働きやすさを追求し、エビデンスを基に、より機能的かつ効果的な提案を行います。

代表取締役社長 竹下 仁氏
以下では、コミュニケーションが活性化するオフィスづくりについて解説しています。
コミュニケーションの不活性とオフィスの課題
オフィスにおけるコミュニケーションは、業務を効率的に進めるためにも従業員が気持ちよく働くためにも重要なものですが、コミュニケーションがうまく取れていない…という職場は決して少なくありません。
そもそも、コミュニケーション不足の職場とは、どのような状態の職場を言うのでしょうか?以下にまとめてみました。
- 従業員同士の会話や交流が乏しい
- 業務の進捗状況やタスクの状況などについて情報共有がしっかりされていない
- 情報共有や交流ができる場を設けても、発信が一方的になってしまう
自分の職場が上記にあてはまっている場合、コミュニケーションが不足していると認識して良いでしょう。
コミュニケーションが取れないとどうなる?
オフィス内で十分なコミュニケーションが取れていない場合、どのような問題が起こり得るのでしょうか?以下でチェックしてみましょう。
業務進捗やタスク状況を互いに把握できない
コミュニケーションが不足していると業務の進捗状況やタスクの状況をきちんと共有できないため、ミスやトラブルの原因となります。また、互いの進捗状況やタスクの状況が不透明だとマネジメントも適切に行うことができないので、全体の業務効率や生産性低下にもつながるでしょう。
業務量やタスクの負担に偏りが生じてしまう
コミュニケーション不足で互いのタスクや進捗状況を把握できていないと、業務やタスクの調整を行うこともできないため、業務負担に偏りが生じます。複数のタスクを抱えて忙しい従業員がいる一方で、手持ち無沙汰の従業員が出てしまうなど、全体を見たときに非効率な状態を招いてしまうということです。
なぜ自分はこんなに大変なのにあの人は暇そうなのだろう…など、従業員間で不満が生じる原因にもなるでしょう。
オフィスの雰囲気が悪化して生産性が低下する
気軽なコミュニケーションをとることができないオフィスは、雰囲気も悪くなりがちです。ピリピリとした空気が流れていたり、質問や確認をとりづらかったりと、居づらさ、仕事のしづらさを感じてしまうオフィスになってしまう可能性があります。
ストレスやモチベーションの低下から、生産性のダウンにつながることも考えられるでしょう。
オフィスが変わればコミュニケーションが活性化する?
オフィスは近年多様化しており、デスクのレイアウトひとつとっても色々なかたちがあります。従来から一般的に採用されている「島型(対向型)」や、近年流行している自由に座れるフリーアドレス型など、職場によってさまざまです。
当然、コミュニケーションの取りやすさや働きやすさも、オフィスによって違ってきます。コミュニケーションの活性化を目指すならば、まずはオフィスから考えてみることも大切です。
コミュニケーション活性化で得られる効果
オフィス内のコミュニケーションを活性化させることで得られる主なメリットを以下にまとめました。
社内の動向を把握できるようになる
コミュニケーションが活性化すると他部署の従業員とも接する機会が多くなるため、自分の業務以外の業務や会社の動向などを知るきっかけが増えます。
こうした機会の増加は、自身のモチベーションアップやエンゲージメント向上にもつながるでしょう。従業員自身にとっても、企業にとってもプラスと言えます。
離職率の低下にもつながる
従業員の定着化は多くの企業にとっての課題です。
従業員が辞めてしまう理由として多いのは「人間関係の悩みやストレス」と言われていますが、社内のコミュニケーション不足は、この悩みに直結します。コミュニケーションが取りづらい職場では、良好な人間関係も築きづらいからです。
以上の理由から、コミュニケーションの活性化は従業員の定着化、離職率の低下にも貢献すると言えます。
生産性の向上
円滑なコミュニケーション環境を整えることで、チームや部署内外の社員ともスムーズに連携できるようになります。そして、社員同士が良好な関係を築くことで、エンゲージメントが高まり会社全体の生産性が向上します。